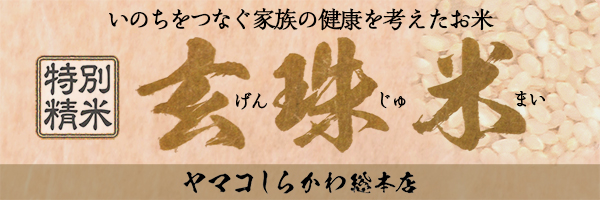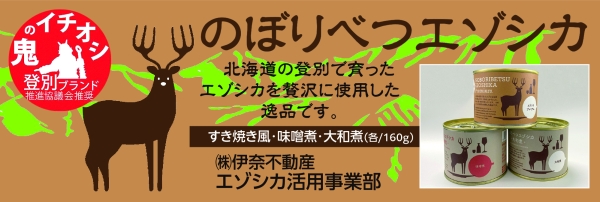高炉存続を願い市民一丸となった運動が展開された
高炉存続へ市民一丸 「希望の灯」まち照らす
国内の高度成長期は、1955~73年の間に年平均9・5%の経済成長率を遂げた。躍進期であった陰で、石油危機が原油価格高騰を誘発。現在のロシア・ウクライナ紛争と同じように、石油依存の日本経済を直撃。値上げと資源不足は室蘭の各産業にも波及した。生産停滞や規模縮小に追い込まれた。
そもそも、2度目の敗戦とも呼ばれる71年8月15日のドル・ショックが、戦後最長の大型好況を断ち切った。戦後の固定為替制度である1ドル360円の超円安に支えられて輸出産業を軸とした日本経済は、ニクソン米大統領が突如表明したドル切り下げにより、73年に変動相場制へ移行した。
船舶や自動車など旺盛な需要拡大に加えて、日本列島改造ブームによる官公需と民間建設需要もあり、先行きを楽観視する傾向が大勢だった。ただ、原材料不足や価格の急騰、人件費増、金融引き締めによる資金難が少しずつ浸透し、微妙な景気の陰りを併せ持っていたことも事実だった。
国道36号室蘭新道のトンネル開通や国鉄の室蘭・青森間コンテナ暫定航路の開設など中核都市としての基盤がそろってきた中で迎えた、第1次石油危機だった。
73年10月に勃発した第4次中東戦争により、石油輸出国機構(OPEC)が原油の供給制限と輸出価格の大幅引き上げを実施。価格は3カ月で約4倍に高騰した。石油を利用する装置型産業に依存していた室蘭で、重油や電力カットによる減産などが相次ぎ、業種問わず売り上げや受注の低下を招いた。
加えて公共事業も減少して、景気停滞の長期化が浮き彫りとなった。不況は市民感情にも飛び火。トイレットペーパーを皮切りに、洗剤など日用品を買い占めるパニック状態は全国的に広がり、室蘭も例外ではなかった。
70年代末から80年代初頭にかけて原油価格は再び高騰。第2次オイルショックで大きな混乱はなかったものの、70年代半ばから室蘭は構造的な不況に見舞われた。深刻な状況下で行政・経済の提携・協調の醸成は必然的なものであった。
各企業が合理化計画を進める中、87年2月に発表された新日鉄の中期総合計画は、室蘭の高炉休止などを含み地元に衝撃を与えた。第2高炉に火入れを行った2年後の衝撃。かつてない危機感の下、文字通りのオール室蘭で、市民挙げての存続を要請し総力を集め活動を展開。5年ほどの歳月を経て、新日鉄と三菱製鋼が出資して設立された北海製鉄が高炉を継承することが発表された。
この時誕生したのが室蘭ルネッサンス。高炉休止をまちの存亡がかかる一大事と受け止めて、市民一人一人が主役になり新しいまちづくりを目指す運動だ。今に続く測量山ライトアップをはじめ、むろらん港まつりでの室蘭ねりこみの開催などを通して、魅力ある地域づくりを市民の目線で行ってきた。
以前は、人同士の肩がぶつかるほどの活気あるまちだった。オイルショックや経済不況、経営合理化の波が押し寄せた。多様な存続運動が行われた中で、地元のシンボルであった高炉の火を消すことなく、つなぎ止めた要因の一つは、間違いなく市民力でもあった。















![写真:[PR]動画クリエイター向けおすすめサービス](/up/img/l/20231204171422384_9847521456.jpg)
![写真:[PR]開運テラス](/up/img/l/20231219162328349_7747194220.jpg)