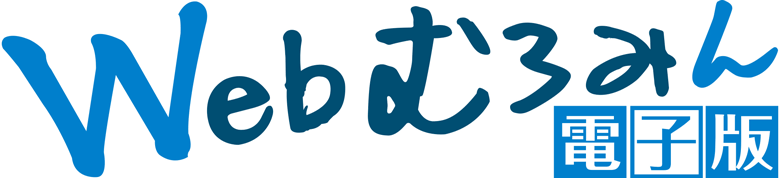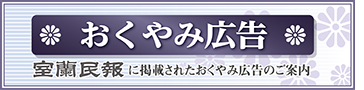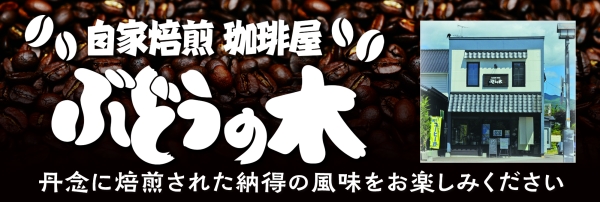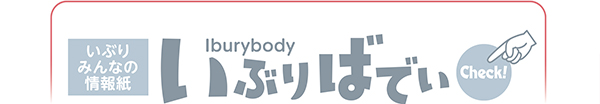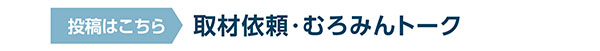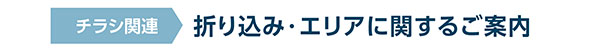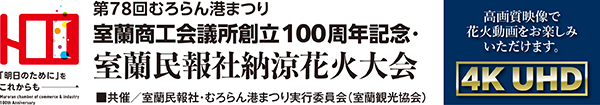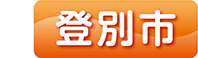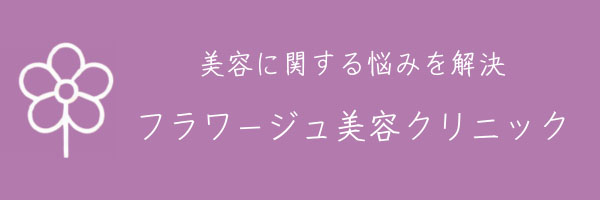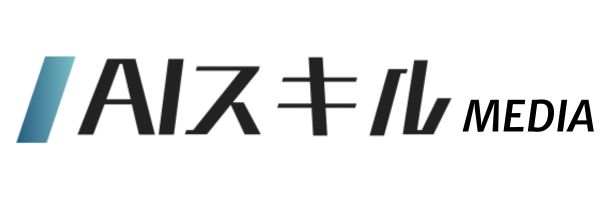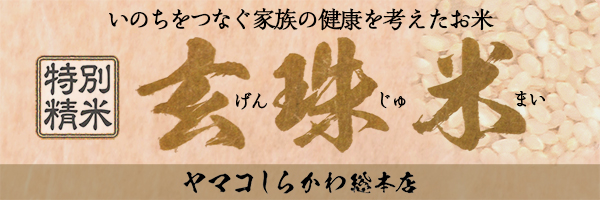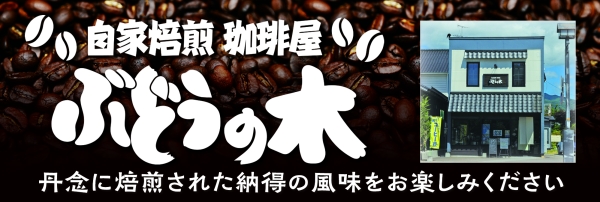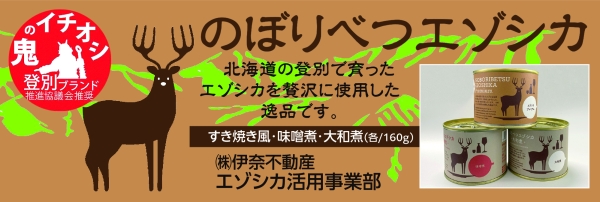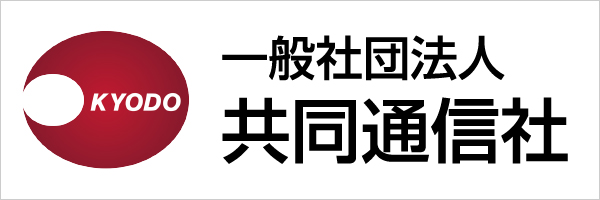尼崎JR脱線事故の発生時刻に合わせ、現場付近で黙とうする人たち=25日午前9時18分、兵庫県尼崎市
◆―― 大惨事の教訓、継承課題
乗客106人と運転士1人が死亡、562人が重軽傷を負った2005年の尼崎JR脱線事故は、25日で発生から20年となった。JR西日本は兵庫県尼崎市の事故現場に整備した「祈りの杜」で追悼慰霊式を開催。
JR西は全社員約2万5千人のうち、事故後に入社した社員が7割を超えた。JR史上最悪の大惨事となった事故の教訓や経験をどう継承し、再発防止へ向け安全対策を徹底していくかが課題となっている。
事故発生時刻の午前9時18分にJR西の長谷川一明社長ら役員が、電車がマンションに衝突した現場に向かって黙とうした。
事故は05年4月25日、兵庫県尼崎市のJR福知山線で、7両編成の快速電車が制限を大幅に上回るスピードで右カーブに進入し、1~5両目が脱線した。線路脇のマンションに衝突した1両目は壁にぶつかり押しつぶされ、2両目は「く」の字に折れ曲がり大破するなどし、多数の犠牲者を出した。
JR西は大阪府吹田市の同社敷地内に事故車両を保存する新施設を建設中で、完成は12月ごろの見通し。
【尼崎JR脱線事故】2005年4月25日午前9時18分ごろ、兵庫県尼崎市のJR福知山線塚口―尼崎間にある半径304メートルのカーブで宝塚発同志社前行き快速電車(7両編成)が脱線、1、2両目が線路脇のマンションに衝突して大破し、乗客106人と運転士が死亡、562人が負傷した。電車は当時の制限時速70キロを大幅に超える約116キロで進入していた。現場には速度超過を検知して自動的にブレーキをかける自動列車停止装置(ATS)が整備されていなかった。国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(当時)は07年6月に運転士のブレーキ遅れを事故原因とする最終報告書を公表した。
◆―― 救えなかった命、悔恨今も 初動捜査の元鉄道警察隊長
たくさんの人の命を乗せた列車が大破した様子が目に焼き付いて離れない。尼崎JR脱線事故で神戸市北区の河井健一さん(77)は兵庫県警鉄道警察隊長として初動捜査に当たった。「救えた命があったかもしれない」。任務に徹し救出活動に加われなかった悔恨の念は今も消えない。発生20年の今月、初めて現場を再訪し祈りをささげた。
「JR福知山線で脱線事故が発生」。2005年4月25日、一報を受け鉄道警察隊本部から現場に急行した。列車が激突したマンションに上がって周囲を見渡し言葉を失った。1両目は駐車場に突っ込んでひしゃげ、全体が見えない。2両目も「く」の字に折れ曲がっていた。「大変なことが起きてしまった」
同隊は鉄道が関わる事件事故の対応が任務。証拠保全のため、隊員には全てを写真に撮るよう指示した。当時はその場で動画を送る機器はなく、幹部とつなげたままの携帯電話で目に入るものを伝え続けた。捜査の肝になる運転士は生死不明。安否を確認するため、先頭車両に張り付いた。
信じ難いこともあった。JR西日本は当日に「線路上に置き石があった可能性がある」と発表した。JRの担当者に話を聞き「不確定な情報を流すべきではない」と止めたが強行された。「生死をさまよう人がそこにいるのに。責任逃れ体質を感じた」。死亡が確認された運転士が、制限を大幅に上回る速度で急カーブに進入したことなどが後に明らかになった。
壮絶な現場を前に思い出したのは、被災者の救出活動に従事した1995年の阪神大震災だった。刑事畑を歩み続け、人の生死に関わる機会は多かったが、震災と脱線事故は全く違うものだった。「人の命はこんなにもはかないものなのか」
今月中旬。あの日以来初めて現場を訪れた。「ここに来る勇気がなかった」。警察官である前に人として目の前の命を救いたかった。そんな葛藤もあった自らの経験とともに「命の尊さ」を今伝えたいと思った。
あれから20年。当時の緊張感や危機感が徐々に薄れていないか。「二度と起こさないために過去を忘れてはいけない」。手を合わせながら決意を新たにした。
◆―― 残された人の心のケアを 遺族支援へ医療従事者派遣
2005年の尼崎JR脱線事故を契機に発足した一般社団法人「日本DMORT」(兵庫県西宮市)は、大規模事故や災害の現場へ医療従事者を派遣し、家族を失った人たちの精神的なケアに取り組んできた。「つらいときに少しでも早く寄り添えるように」と関係機関と連携しつつ人材育成を進めている。
05年4月25日、事故現場では救急治療の優先順位をつける「トリアージ」が行われた。救急隊員が負傷者の呼吸回数や意識の有無を確認し、4段階で色分けする「トリアージタグ」を手首に装着。医師が詳細に診察し、死亡と判定された人には黒色のタグをつけた。
神戸赤十字病院の心療内科部長で、日本DMORT理事長の医師・村上典子さん(62)=神戸市=は事故から半年後、受診した遺族から悩みを打ち明けられた。「息子は黒タグを付けられたが、もし搬送されていたら助かっていたかもしれないと思ってしまう」。現場では遺族への配慮が不足していたと感じた。
06年、災害医療の学会で発表すると、多くの参加者から反響があった。ある医師に「米国では災害時に検視や遺族への対応を行うDMORTという組織がある」と教わった。「つらいときに少しでも遺族に寄り添えるように」と同年、同じ志を持つ医師らと研究会を設立。遺体安置所で家族を亡くした遺族への対応を学ぶ研修会を全国で開催した。
13年の東京・伊豆大島の土石流災害で初めて看護師らを派遣。だが警察の許可が下りず遺体安置所に入れなかった。16年の熊本地震では活動を知る兵庫県警が熊本県警に協力を依頼。初めて遺体安置所に入り、泣き崩れる遺族の話を静かに聞いた。「関係機関の理解がなければ難しい」と17年に法人化。これまで10府県の警察や海上保安庁と連携協定を結んだ。
24年元日に起きた能登半島地震では看護師ら12人を石川県に派遣し、1月4日から11日間で126家族に対応。遺族が対面するまでに遺体の顔を拭き、ばんそうこうを貼って傷を隠した。声をかけるのもはばかられるような緊張感に包まれる中「ありがとう」と声をかけられたこともあった。
対応した遺族と再会することはほとんどないが、熊本地震後には活動の普及を願う手紙が届いた。「いざという時、その場にいる人たちが遺族ケアを自主的にできるよう浸透させていきたい」と村上さんは語った。